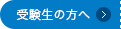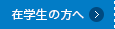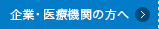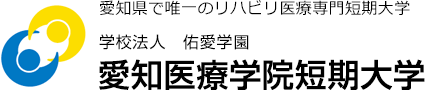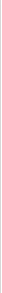教員リレーコラム
「小説」
舟橋 啓臣 [理学療法学専攻]
東海地方はほぼ満開、東北にも開花宣言が下されたので、もう一カ月もすると仙台などでも満開の便りが届くでしょう、と言ったような桜前線の案内が毎日のように流れていたのは、つい最近のことである。満開の期間はせいぜい1週間で、桜はあっという間に散ってしまった。惜しまれて散りゆくことが桜の良さだと言うが、いかにも短期間である。今年は春の訪れに確かさがなく、いつまでも寒かったせいで、桜を待ちわびる気持ちが例年よりも強かったのか、道路のあちこちにピンクの絨毯のように敷き詰められた花びらの群れや、池に浮かぶ花筏を見ると、もう少しの間、枝に咲き誇る満開の姿を眺めていたかったのにと残念でならない。「願わくば 桜の下にて春死なむ そのきさらぎの望月のころ」。西行法師が吉野の桜を歌ったものである。旧暦では2月の頃に桜が満開になったのであろう、月と花を無常のものと捉え、西行は辞世の句としてこの歌を残したと言われる。
立原正秋という作家がいた。「能の家」や「剣が崎」、「紬の里」や「薪能」などで知られる。この作家と出会ったのは26歳の頃で、以来、全ての作品を読みあさるうちに、大方の小説の底辺を流れる、お茶や能、紬を中心とした着物、焼き物などの、日本古来の美に魅了されてしまった。その影響で裏千家の茶の湯の指導を受け、能を鑑賞する会に入り、熱田神宮の能学会館にも出かけた。幾つかの小説に、立原が居を構えていた鎌倉の色々な場所が登場するため、鶴岡八幡宮や雪の下、扇ガ谷や化粧坂などを何度か歩くことになった。八幡宮の近くの鎌倉彫の店や、鎌倉駅の小町通りにあったレストランも訪ねた。彼の小説を読むことで、余韻とか無駄を省くといった、日本の言葉の美しさを知った。また、日本の(特に中世)の美についての探究心を養ってくれることになった。彼は早稲田大学で中世文学論を勉強していたようで、古典が幾度となく引用されている。自分も古典に魅かれるところが強かったため、彼の作品にのめり込むことに抵抗はなかったようである。食道癌で死んだのだが、直前まで食べることに執着していたようだ。作品の中で無常を扱うものが少なからずあり、紹介した西行法師の辞世の句も、どれかの小説に引用されていたものを記憶していたのである。小説は読者によっては、どれだけの影響を受けるか計り知れないものがある。高校2~3年の頃、受験勉強に打ち込むべき時期であるのに、太宰 治にはまってしまい、学校の図書館で作品を読みあさる姿を担任の先生に見つかり、こっぴどく叱られたった覚えがある。要するにのめり込みやすい性格のようであるが、気に入った作家に出会え、あんなにも身も心も傾倒してしまった頃のことを思い出すと、今でも懐かしく幸せな気持ちに浸ることができる。